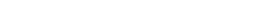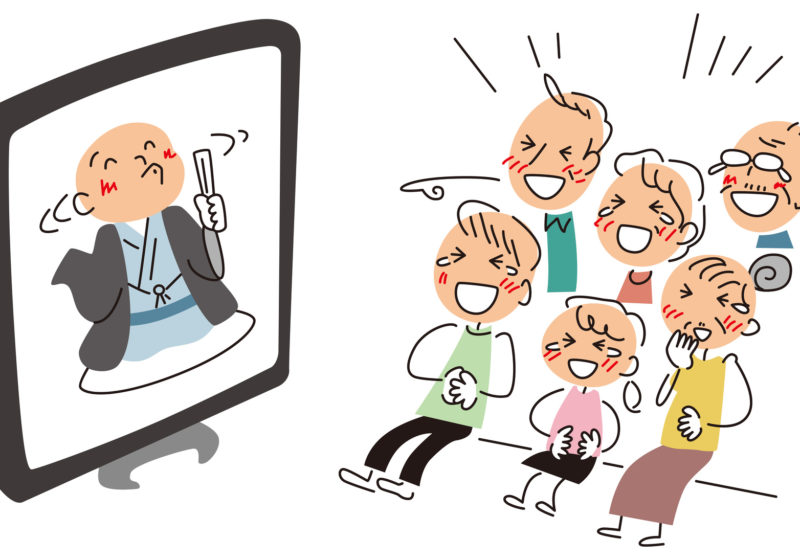笑いは健康の秘訣☆彡
皆さま、こんにちは!
今日から3月ですね![]()
![]()
先日、「水戸まちなか寄席」に水戸ヤクルトの化粧品をご愛用していただいているお客様をご招待させていただきました。
内容は、落語家、桂雀々さん・笑福亭茶光さんをお招きしての落語会。
しっかり、コロナ対策を取られた上で安心して参加することが出来ました。
さすがプロ。あっぱれ!
巧みな言葉遊びと身振り手振りの表現力で、あっという間に話に引き込まれました。
たちまち会場は、爆笑の嵐。
「#空気を変えていく」
そんな技を私も持っていたら…と憧れの眼差しで聴いていました。
お腹を抱えて笑うお客様の姿があちらこちらで、見受けられ
とっても満足!おなかいっぱい胸いっぱいの様子でした。